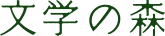これから先、カフカという文学者について、考えていきたいと思っています。というのも、カフカの作品には、ものすごく共鳴する部分があるように思えるからです。きっかけは、カフカの「城」という文庫本のあらすじを見たときでした。そこに、職業だけが唯一の存在形式となった世界における疎外、という部分があって、これに思わず、大いに反応してしまったからです。これはまさしく、自分そのものなのではないかと思ってしまったのです。ただとりあえず、自分はまずこの小説の概要を知りたいと思って、最後の後書きから読み始めました。このあとがきがカフカの文学の要約となっており、ものすごく傑出した内容で、読んでいて心がものすごく反応してしまいました。というのも、あとがきに描かれていたのはまさしく、自分が置かれている環境そのものだったからです。そう、カフカの文学の前提になっている環境は、自分のものとほとんど同じなのです。自分は今まで、他者に対して「絶対的な隔絶」を感じてきました。どうしても、他人に触れられないのです。他人は硬く、その現実存在を閉ざしていて、決してその内側に入っていくことが出来ません。そもそも他者に心というものがあるのかすらも覚束ないほど、他者が表面的なものとしてしか立ち上がってこないのです。そんな「絶対的な隔絶」は、カフカの世界においては、「城」として立ちはだかっているように思えてなりません。城は決して、その門を開くことがありません。城の門は固く閉ざされたままです。自分と城は、決して出会うことがありません。たとえば、分子が互いに出会い、結合し、何か新しいものに生まれ変わるような、そういった一連の現象のきっかけは、どこにもありません。他者は絶対的な不可能であり、城は絶対的な不可能なのです。そんな不可能によって支配されているカフカの文学の世界に、どうしても反応してしまいました。これは、自分の環境そのものなのです。自分は世界に対して、一生涯入場することが出来ないように思えます。どこにも所属することなく、一生どこかではぐれて生きていく運命を強いられているように思えてなりません。
しかし、おそらくなのですが、自分はカフカとは全く違う人間です。それは、人間としての実存そのものの問題です。結局カフカはどこにも所属することが出来なかったのですが、カフカにとってはどうやら、無所属がそのまま虚無へと繋がっていくようです。カフカの世界においては、人間の現実存在の中身は所属によって得られる、という前提が存在するようなのです。しかし自分の場合は決してそうではありません。自分は決して、虚無ではありません。それが自分が今まさに、「自分のために生きて自分のために死のうとする」きっかけになっているように思えるのですが、そのような生き方が出来るのは、自分の内面に確かに何かが存在しているからです。それが存在している以上、自分は決してゼロではないのです。しかしカフカの場合は、ひょっとしたらゼロだったのかもしれません。というのも、カフカの文章を読んでいる限り、あまりにも散文的で味気ないように思えるからです。これはどういうことなのかといえば、全く詩的な表現ではないということです。どこかの取扱説明書に出てくるような文章が長々と続いていくのが、「城」という作品の特徴でしょう。しかしそれはやはり、カフカの事務員としての本質を体現した特徴でもあるように思えます。カフカはやはり、ゼロとしての運命を生き続けたのではないでしょうか。しかし自分は、ゼロではないのです。だからこそ、カフカとはまた変わった生き方をするようになるように思えます。城に入れなかったら、迂回すれば良いのです。迂回した先にある、接触できるものの中にも、素晴らしいものはあるはずなのです。


2025/09/22 20:00