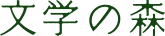【6月20日文学の森ライヴ配信について】
2025年6月20日(金)、文学の森にて「平野啓一郎×苫野一徳──プラトン『饗宴』から考える“愛とは何か”」というライヴ配信が開催されました。
私は以前に『饗宴』を読んだことがありますが、哲学に詳しいわけではなく、いち学生としての立場から今回の対談を拝見しました。文学の森には5月から参加しており、ライヴ配信を視聴するのは今回が初めてです。
記憶をたどりながらにはなりますが、印象に残ったお話や、お二人の対談の雰囲気について、このレポートにまとめてみたいと思います。
【お二人について】
お二人の対談では、文学者・作家と哲学者・教育者というそれぞれの立場が一貫しており、その視点から語られる意見に個性があって、とても興味深く感じました。
冒頭で苫野さんは、これまで哲学を通して考えてきたことを3つ挙げていました。1つ目は「良い教育とは何か」、2つ目は「良い社会とは何か」、そして3つ目が「愛とは何か」です。哲学とは、物事の本質に迫る学問であり、こうした問いを通して本質を探っていく営みだとお話しされていました。
今回の対談は、この問いを軸に進められていきます。
【概要】
大きく3つの印象的なポイントに分けて記していきたいと思います。
まず1つ目は、「哲学と文学」についてです。
苫野さんのお話で特に印象的だったのは、次の2点です。
①かつて「普遍性」や「本質」といった言葉が敬遠され、絶対的な価値は存在しないという前提のもと、物事を相対的に捉える視点が重視された時代があったそうです。このような視点には一定の意義があるものの、「確かなものは何もない」という姿勢を繰り返し続けてしまうと、批判の根拠をも失いかねず、最終的にはファシズムや暴力を肯定しかねない社会につながってしまうのではないか、という危機感が語られていました。
②また、文学と哲学は「よいものを作品として世に出す」という点では似ているものの、そのアプローチは対照的であるという指摘も印象に残りました。文学は、具体的な出来事や人間の姿の中に普遍性を見出しますが、哲学は普遍そのものを論理的に追究していきます。こうした違いがあるため、哲学的な才能と文学的な才能が同時に備わっている人は非常に稀である、とのことでした。
この話に対して、平野啓一郎さんは文学の立場から次のように語られていました。
①たとえば芥川龍之介の作品では、個性的な人物が個性的な体験をしているように見えても、結末では「人間のエゴイズム」や「人間の本質的な問題」に帰着してしまう傾向があります。これ自体が悪いわけではありませんが、登場人物の個性が物語の中で薄れてしまうように感じられることもある、という指摘でした。また、これまでの文学、特にリアリズム小説は、社会の矛盾を描くだけで一定の役割を果たしていました。しかし2000年代以降の読者は、すでにそうした矛盾を理解したうえで、「ではどうすればよいのか」という次の段階の答えを求めているように思われる、という見解も示されていました。
②さらに、文学は具体性を伴う表現でありながらも、どこかに普遍性がなければ読者を惹きつけることはできないという点にも言及がありました。読者は多様である一方、小説という形式は一つのまとまった形に仕上げなければならず、小説家には繊細なバランス感覚が求められるとのことです。また、「いきなり誰かに正しいことを語られても、人はすぐには受け入れられない。むしろ反発が生まれる」という発言も印象的でした。たとえ書物であっても、読者の中に生まれるフラストレーションは、物語のどこかで受け止められていなければならない、という考え方が示されていました。
2つ目は、「プラトンや『饗宴』」についてです。
①『饗宴』は、「良きものを永遠に我がものにしたいという欲望がエロスである」と簡潔に定義しており、それが非常に的確であると評価されていました。物語は登場人物たちの語りを通して進み、ディオティマの話に移行し、最終的にソクラテスの思想へとつながっていきます。この構造は「アウフヘーベン(止揚)」という哲学的な概念によって説明されていました。アウフヘーベンとは、「あまり本質的でないものは捨てながらも、価値あるものは保存する」という意味であり、議論の中で重要なポイントが徐々に選別されていく流れがあるとのことでした。
各登場人物の発言は以下のように整理されていました。
・パイドロス:愛する者のためなら死ねるという、自己犠牲の精神を語る。
・パウサニアス:正しく愛し、正しく愛されることの重要性を説く。
・エリュクシマコス:愛とは調和を導く力であると論じる。
・アリストファネス:人間はかつて一体だった存在であり、愛は失われた半身を求める行為であると語る。
・アガトン:恋は人を詩人にし、創造力を引き出すものだと述べる。
これらの多様な愛のかたちが、ディオティマの語りによって止揚され、愛の本質へと至っていくという構造になっているとされていました。
②また、ディオティマの「エロスは美しいものを求め、それゆえに美の中に子を成すことを求める」という説明についても議論がありました。最初は、生物学的な視点に偏っているように受け取られる可能性もあるという意見がありましたが、「子を成す」ことは単なる生殖ではなく、「永遠化の欲望」の象徴と捉えることができる、という解釈が示されていました。これは、アガトンの「恋は人を詩人にする」という考え方とも通じており、詩や芸術を生み出す行為そのものが、永遠性への希求であると考えることができる、という見解でした。
3つ目は、「教育」についてです。
まず苫野さんは、ソクラテスの生き方そのものが弟子に大きな影響を与えているという点に触れ、それこそが最高の教育のあり方ではないかと語っておられました。ソクラテスは「美とは何か」が分からないからこそ、それを対話を通じて考え続けた人物であり、そのように無知から知へと至ろうとする姿勢こそが、教育のもっとも純粋な形だというお話でした。
苫野さんご自身も、現在「対話の場」を作る活動に取り組まれており、そのなかで特に重視しているのは、「答えのない問い」に対して、言葉にできたり、あるいは“なんとなく分かったような気になる”という体験を得ることだと語られていました。
このような苫野さんの発言に対し、平野さんは、「無知を自覚することはとても大切だ」と応じたうえで、現代社会における“対話”の質について問題提起をされていました。近年は、しっかりと対話を重ねることよりも、「いかに相手を言い負かすか」「論破できるか」ということに重きが置かれがちであるが、そうした風潮には強い違和感があると述べられ、「そんな世の中って嫌だよね」という率直な言葉が印象的でした。
また、『饗宴』においては少年愛というテーマが一つの軸として扱われていますが、この点についても議論が交わされました。
苫野さんは、少年愛という価値観は現代の感覚とは大きく異なっており、教育現場において「身体的接触を通じた教育」という考え方は、現代では受け入れられないと述べられていました。しかし一方で、「学者にわが子の頭をなでてほしい」と願うような感覚には、「触れられることを通じて、何か知的なものが得られるのではないか」という潜在的な期待があるのではないかと分析されていました。そうした願望のかたちが、少年愛とは異なる形で現代にも受け継がれているのかもしれない、という指摘が印象的でした。
加えて、「エロス的な要素を取り除いたうえで、美しく知的な少年をより賢く育てたいという願いは理解できる」との見解も語られていました。
これらのやり取りを踏まえて、平野さんは「近くにいるということに学びがある、ということですね」と応じておられました。
【感想】
私は、正直これまで哲学に対してどこか忌避感を抱いていました。
答えのない問いについて延々と考えることに、どこか「時間を浪費しているのではないか」という感覚を拭えなかったからです。実際に『饗宴』を読んだ際も、どこか批判的な目線で読み進めてしまい、「結局これは何が言いたいのか」と納得できないまま読み終えてしまいました。
しかし今回、お二人の対談を拝聴することで、『饗宴』がいかに文学的であり、また哲学としても深い魅力をもつ作品であるかを理解できたように思います。平野さんのお話にはっとさせられる瞬間が何度もあり、苫野さんのお話からは「考えることの価値」や「対話を通じて知に近づいていくことの意義」を改めて教えていただきました。
哲学を遠ざけていた自分の姿勢を少しずつ変えていきたいと思える、貴重な時間となりました。


2025/06/30 10:05